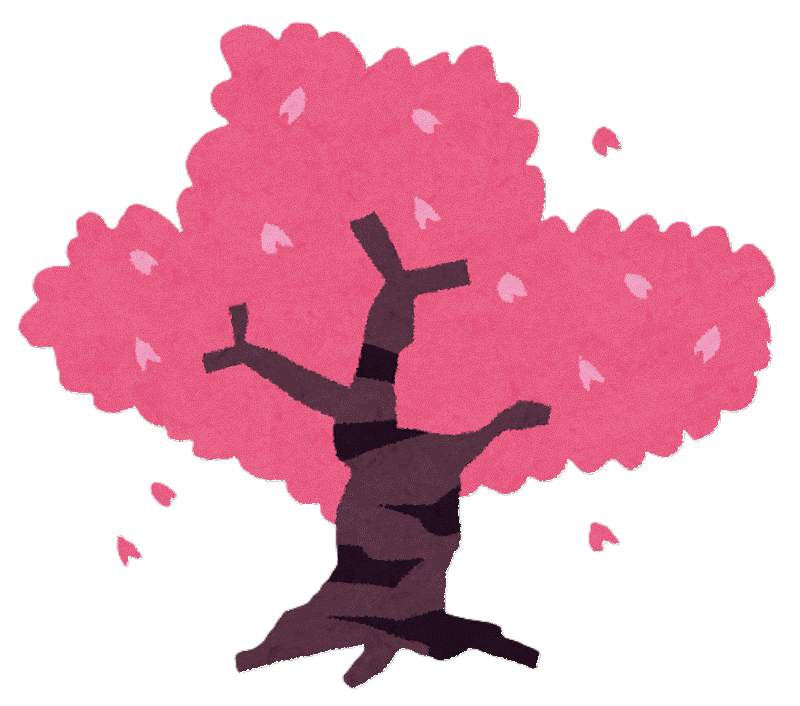入学式といえば桜咲く4月が定番ですが、4月始まりというのは日本独自の文化だとご存知でしょうか。実は日本のように4月を新学期の始めとする国は珍しく、世界では9月始まりが主流です。
そこで今回は、なぜ日本の学校が4月に入学するようになったのか、その理由をご紹介します。
今でこそ4月入学は当たり前になっていますが、昔からそうだったわけではありません。
江戸時代の寺子屋、私塾、藩校などでは特に入学の時期を定めず、随時入学できました。
やがて、明治維新で西洋の教育が導入されると、高等教育では9月入学が主流となりました。ドイツやイギリスの教育制度を参考にしたためといわれています。
ではなぜ日本では学校の新年度まで4月に合わせたかというと、主に2つの理由があります。
ひとつは、明治19年(1886年)に国の会計年度が「4月-3月」になったことに起因します。学校運営に必要な補助金を政府から受け取るためにも、会計年度に合わせたほうが都合がよかったわけです。
そしてもうひとつの理由としては、軍隊の士官学校の入学時期が4月となったことがあげられます。士官学校の入学時期が4月に変更となると、9月始まりだった一般の学校は、優秀な若者が陸軍に先取りされてしまうかもしれないと危機感を抱き、こぞって4月始まりへと変わっていったようです。
グローバルスタンダードの一環として日本の新学期も9月始まりにすべきでは、という意見も多く挙がっていますが、皆さんはどう感じますか?